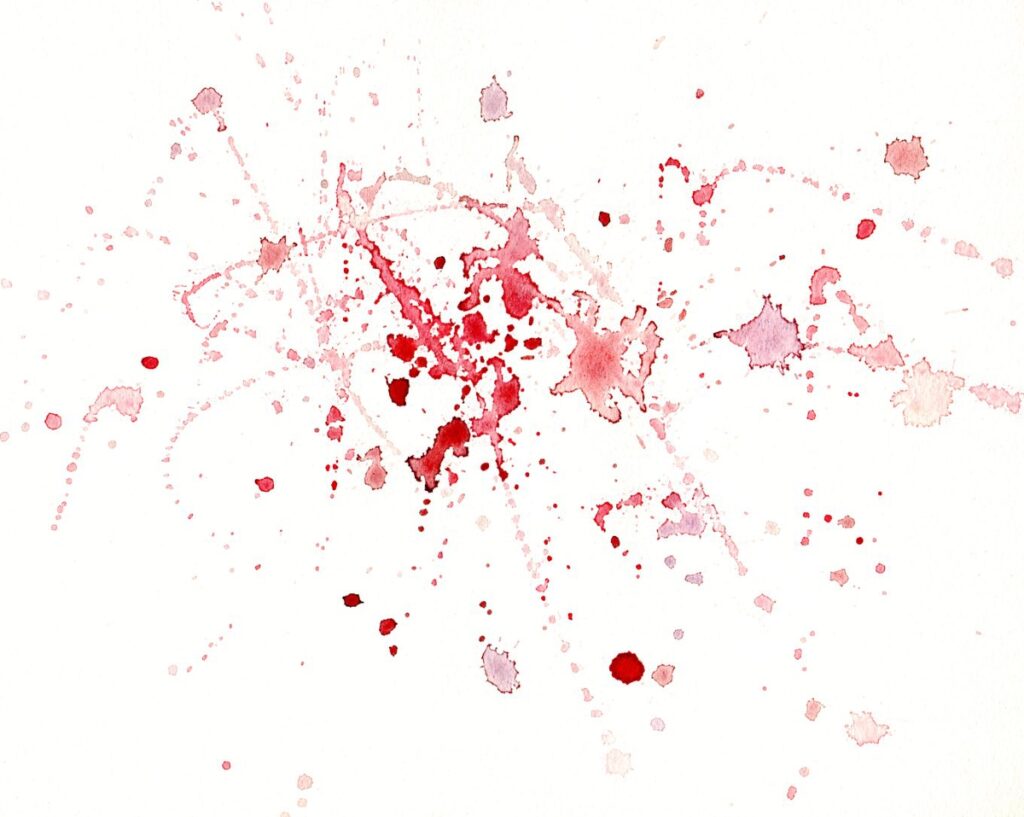人間は結局二つの因子や原因による産物であるという考え方が根づいています。今まで申し上げてきたのは、その一つ、遺伝とか生まれつきのもの、素質ということです。もう一つの因子は環境とか境遇ということです。人間の振る舞いは遺伝と環境、素質と境遇という二つの力を平行四辺形にあてはめ、その合力であるという産物として捉える見方です。しかし、遺伝の研究でよくある一卵性双生児の研究から、人間がいかに共通な因子を持とうと、同じ家族環境で育てられようと、違った人間として成長することがわかっています。
人はもちろん遺伝にも環境にも依存はします。この両方の枠の内側で自由に動きまわることができるわけです。この自由を疎かにしたり、抑圧したり、野放しにするとその報いを受けないわけにはいきません。人間には自由を求める本性があります。人間精神の自由さ、反抗力ともよべる力を呼び覚ますことが大切なのです。これがいわゆる「生きる力」という考え方であったはずです。
遺伝と環境の向こう側、彼岸に第三のもの、これが反抗力であり決断力であり向上心だと思うのです。学校教育はこの第三の力を教科において、部活において、さまざまな発表において養しなわせようと努力しています。生きる理由を見つけるのが子どもの学習ということです。資質を高めること、磨くこと、境遇を変え克服することが教育の目指すことです。教室では時間を使ってこのことを教えるのです。資質と境遇という平行四辺形を拡大していくことであります。
虐めは、遺伝と境遇、そして人間の自由の関係で生まれる複合的な現象です。社会的な産物ともいえます。このような相互関係を考えると、学校という場が虐めを予防するとか対応するというのはすでに限界があるのです。学校がこの複合的である種病理的な現象に対応する能力はあるでしょうか。教師と養護教諭、そして管理職だけが専従という体制でこの社会的病理現象に対応できるでしょうか。ときどきスクールカウンセラーがやってきても、スクールサポーターがいても所詮焼け石に水ではありませんか。
複合的な虐めの現象に対応するには、専門性を集めた知恵が必要なのです。たとえば、ソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、特別支援コーディネータが専従して予防や対応にあたらないといけないのです。ソーシャルワーカーは、貧困家庭やシングルマザーやファーザーへの目配りや支援、福祉や警察機関との連携を、スクールカウンセラーは子どもや保護者に対する応用行動分析などの心理社会的なアプローチ、社会性スキルトレーニングなどを使って支援をするのです。特別支援学校などへの進路の可能性の提案、行動上の課題が深刻なときは、医療機関との連携などや、神経の働きを調整し症状をコントロールするコンサータとかストラテラなどを服用する薬物療法などの知識が必要かもしれません。
現在、特別支援教育の主たる話題は、発達障害です。こうした子どもが増えたということではなく「発達障害と診断される人が増えた」と解釈されるのが一般的です。発達障害自体の認知度が高まりに伴い、以前であれば「少し変わっているな」という程度で見過ごされていた子どもが、保護者やご本人の気づいて報告されるようになりました。発達障害は治ることはありませんが、適切な療育や訓練で症状は改善できるようになりました。おさらいですが、自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群は知的遅れのない自閉症のタイプ、読字、書字障害などの学習困難、そして通常AD・HDと呼ばれる注意欠陥多動を指します。こうした特別なニーズのある子どもに特別な対応方法があり、それを実施する専門性のある教師らが対応しています。
繰り返しますが、子どもの虐めなどの複合的な問題は、専門性のある職員とが担任教師と協力して対応することです。その場合、特別支援コーディネータが中心となり担任などからの個々の生徒の発達課題などを集め、保護者を交えて個別の指導計画が作られるはずです。それをスクールサポーターも理解し指導に取り組むことができるのです。現在のように、気になる子をスクールサポーターに丸投げし、預けるような状況ではいけないのです。スクールサポーターの役割を定めて責任を自覚させることです。
虐めや子どもからの相談には、教師が一人で対応することではありません。根本的な解決には、教師による小手先の対応では解決できません。教師の任務は、教科指導の準備をしっかりやり、一人ひとりこどもの学習の進捗を把握し、保護者との対話なのです。教科指導によって人間の価値や命の大切さ、生きることの大事さ、将来の夢を膨らませることです。そして誰もが人生の主人公として生きる存在であることを教えるのです。